いかに集めるか
実店舗を運営するばかりでなく、ネット上でSHOPを展開する、プラットフォームを運営するなど、
多くの事業でいかにカスタマーやオーディエンスを集めるか、その中からいかにリピーターであるファンを作るかは重要な課題です。
ご存知の通り、広島東洋カープ(以下 広島カープ)は、長らくの動員数低迷から脱却し、
今では席も取れないほど人気球場を作り上げました。
その成功要因は何なのでしょうか。
広島カープの戦略には、集客のエッセンスが詰まっています。
そしてその戦略はプラットフォームビジネスや集客ビジネスに応用できる戦略なのです。

広島カープの集客率の実態
広島カープの観客動員はたしかに伸びています。
2014年〜2017年を比較しますと、伸び率は11.6%です。
阪神が10.5%、巨人は−0.6%ですから、すごい数字ですね。
しかし、実はさらに上がいるのです。
DeNAは19.3%、ヤクルトは18.3%です。
決して広島カープだけが伸びているわけではありませんね。
ところが、ホーム以外(ロードゲーム)での観客動員は
広島カープがダントツの1位/237万8140人、
伸び率は2位89.3% (1位は阪神の90.5%)と、圧倒的な数字です。
この辺りにも秘密がありそうです。
球場建て替えの決断
広島球場が建て替えに至った背景には、球団の、球界の危機がありました。
広島カープに危機感を与えたのは
・セパ合併、1リーグ制への移行が検討された
これらのことが要因と言われています。
その背景には球団の観客動員数の減少がありました。

減り続けていた観客動員数が、12球団で唯一100万人を割り込んでしまったのです。
2004年の巨人が374万人ですから、収益的にも大きな差がありますね。
アメリカの手法を導入
オーナーである松田氏は、実は早くからアメリカの球場運営手法に目を向けていました。
日本では東京ドームの建設以降ドーム球場ブームでしたが、
アメリカではすでにドーム熱は去り新しい発想の球場『ボールパーク』が生まれ始めていました。
アメリカのビジネス手法は日本の何年も進んでいると言われます。
古くはダイエーのGMS(総合スーパー)戦略が有名ですね。
アメリカの手法をいち早く取り入れたダイエーは
飛ぶ鳥を落とす勢いで他のスーパーを圧倒し急成長しました。
(事業立地の変更が上手くできなかったことから衰退してしまいましたが)

では『ボールパーク』とはどのようなものなのでしょう。
マツダスタジアムは「ボールパーク」
野球を楽しむ場所に変わりはないのですが、ボールパークは球場に留まらず、アミューズメントパークとして成り立つようにコンセプトされたいわゆる娯楽施設です。
以下のような「ボールパーク」としての特徴をマツダスタジアムは備えています。
いろいろな席が用意されている
普通の野球観戦用シートはもちろんありますが、他に
「寝ソベリア(寝転んで観れる席)」「ファミリー席」「無料席」「砂かぶり席」「パーティーフロア」「びっくりテラス(BBQが出来る)」
などいろんな席がマツダスタジアムにあり、それぞれの楽しみ方があるのです。

球場内の行き来が可能
普通の球場では外野席と内野席、バックシートなどの行き来は出来ないようになっています。
しかし、ボールパークである広島 マツダスタジアムはすべて行き来が可能となっているのです。
いろいろな場所で試合を楽しめ、飲食を楽しめ、アトラクションを楽しめるのです。
また、街との一体感を出し、球場内を電車からも見えるようにするために、北側(JR側)が大きく開いた形にしているのも特徴ですね。
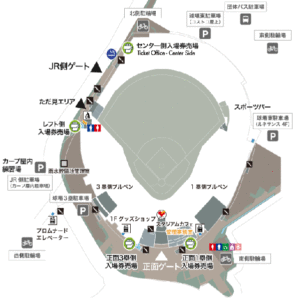
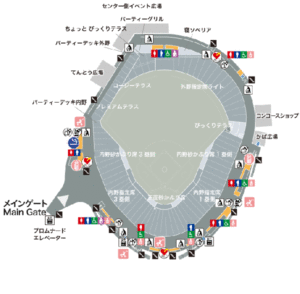
スタジアム1階・3階のMAP(MAZDA Zoom-Zoom スタジアム 広島HPより)
休日も楽しめる
普、球場は試合のないときは閉まっています。たまにコンサートなどで使用することはあるでしょうが、
一般の人はあまり訪れることはありませんね。
マツダスタジアムは休日も開放していますから、散歩コースになったり、カフェに入ったり
はたまたアミューズメント施設があったり、お化け屋敷まで。
地元の人がいつでも楽しめるようになっています。
地域に根ざすこと、これが集客ビジネスの秘訣です。
マツダスタジアムの仕様からビジネスを考える
球場とはまさにプラットフォームそのものです。
店舗(ネット上も含む)の場合はそれらの店舗そのものです。
マツダスタジアムは従来のプラットフォームである球場の概念を上手く変えています。
商品販売のサイトで言うなら、商品を買う人以外も訪問したくなるように仕組みを変えたのです。
また、シートの種類を増やしたことは、方法や選択方法、顧客の関わり方そのものを変えることに当てはまります。
今までの当たり前と思っている概念を変えること、主要な目的を持った人以外にも興味を提供することが
実店舗やプラットフォームに多くのカスタマーを呼ぶ秘訣なのではないでしょうか。
たとえばコンビニなどはどんどん提供できるものを増やしていますね。
商品が買える以外に、
・払い込みができる(役所・銀行)
・本が買える(本屋)
・チケットが手に入る(チケット売り場)
・買ったものを食べることができる(飲食店)
・入出金ができるなど(銀行)
いろんな人が訪れる仕組みを作っています。
単にターゲット顧客を増やすのではなく、ターゲット顧客を絞りいろんな角度から いくつものニーズを割り出し、それらのニーズに対応するサービスを増やしていくことでも相乗効果を得られるのだと思います。
周囲を巻き込むこと、異業種、異文化、地域といった周囲を巻き込み、多くのニーズを取り込むこともまた
実店舗やプラットフォームの魅力をアップさせるのではないでしょうか。
その他にも多くの秘訣があります。
他の収益源も作る

グッズ販売にも力を入れています。
まず、Tシャツの種類が半端ないのです。そしてサイクルが早い。
たとえば、新人が初勝利をあげた時など、次の日にはその選手のお祝いTシャツが販売され、
飛ぶように売れています。200勝・2000本安打などもそうです。
(ビールかけTシャツなどは数日で24万枚売れたとのことです)
アイテム数は年間で1,000アイテムにものぼるそうで、年間50億円以上の売上げです。
話題として取り上げるタイミングを逃さず、瞬時に対応することが重要なのだとわかります。
タイミングを見極めることで、大きな収益源を確保できています。
タイミングは大事ですね。
いかにタイミング良く顧客アプローチをしていくかが重要ですが、
そのタイミングをいかに多く作っていくかも、集客をする上で重要な要素なのですね。
地元企業との連携

休日に入れるようにしたり、アミューズメント施設を作ったりして地域との連携を行っていることは前述しましたが、
実は地元個人だけでなく、地元企業とも連携しているのです。
原則として1企業1商品としていますが、地元の多くの企業が球団のグッズを製造販売しています。
商品内容は特に決まっていません。大ヒットしたマスキングテープやふりかけなど多種多様。
球団はロイヤリティーが入りますし、企業は自社商品の宣伝にもなる。WIN-WIN の関係を築いているのです。
球団のグッズ以外に多くの広島カープ関連アイテムを持つことは、それだけ多くの人の目につくということですね。
地元と一体感を持って
地元の企業などとコラボすることで、地域の活性化にもつながります。
球場を単体と考えず、地域の一部だという考えかたは、不足部分を補いあえる関係さえ築けていれば、すごくメリットを生むことになり得ます。
実店舗においてはイメージしやすいですが、プラットホームにおいても同様です。
プラットフォームに不足の部分を他社商品やサービスで補えれば、プラットホームの価値は何倍にも上がるでしょう。
地元地域や特定の業界などに絞ってオープンイノベーションを行なっていくことは、そういった意味で重要ですね。
北海道ボールパーク(追記)
2023年3月に、日本ハムが所有運営する、日本ハムファイターズ本拠地としての「エスコンフィールド北海道」を中心とした
【北海道ボールパークFビレッジ】がオープンしました。
マツダスタジアムと同様に、いろいろな形での野球観戦が可能なことに加え
(北海道ボールパークではホテルの客室からの観戦に加え、サウナに入りながらの観戦なども可能です)
北海道のグルメを堪能できる飲食店や、ブルワリーも備えています。
近隣にはドックパークや大規模アスレチック場、サイクリング施設など、
約32ヘクタールの壮大な土地にエンターテイメントやウェルネスなどを備えた大規模なボールパークとなっています。
北海道Fボールパークは、所在地である北広島市をはじめ周辺17市町村や関係機関、学識経験者などがが連携し、諸課題の解決のために話し合い、北海道の価値魅力向上及び成長・発展に寄与することを目的として開業した、壮大なボールパークです。
もちろん、マツダスタジアムと同様の、地域の活性化を狙った総合施設です。
ボールパークだけではなく(ボールパークの一環として)居住区も組み込み、地域への人口導入を目論んでいることは、北海道ならではの戦略だと思います。
実際に、分譲マンション118戸は完売、倍率は平均10倍であったそうです。
さらに駅前には新築分譲マンションを建築予定で、今後も住民は増加し、活性化は進んでいくと考えられます。
ボールパークは、野球を核として、地域・自治体との連携を行い、地域の課題を解決することを目的とすることで、大きな力を発揮することになるのですね。
それにしても、札幌ドームがあるのに、日本ハムファイターズはなぜ新球場を建設したのか、少し疑問に思っていましたが、
実は札幌ドームは札幌市の所有だったそうです。(みなさまはご存じだったと思いますが無知でした。。。汗)
日本ハムファイターズは自前の球場を持ちたいという意向はあったので、ボールパーク構想(2015年よりスタートしたと聞いております)はまさに渡りに船の状況だったのではないかと思われますね。
広島カープの戦略は他にもあります。
「カープ女子」についてのブログは②へお願いします
-

-
広島カープの戦略から集客ビジネスの成功要因を読み解く② カープ女子
カープ女子の実態 広島カープといえば、カープ女子が非常に注目されていますね。 何故急にカープ女子が増えたのでしょうか。 実は広島カープは、昔からレディースカープという女性のためのファンクラブを作り、女 ...
テイクオフパートナーズ代表
MBA
2級知財管理士
2級ファイナンシャルプランナニング技能士
西谷 佳之
いつもご覧いただきありがとうございます。
他各種ビジネスセミナー、個別コンサルタント等を賜っております。
過去講演題目(抜粋)
・スモールベンチャーファイナンスのリアル
・ドラマ「陸王」から紐解く 経営ビジョンが叶える会社の生き方
・オープンイノベーション推進におけるクラウドファンディングの活用について
・銀行から融資を受けるポイントとは
・財務分析の勘所
・女性のためのクラウドファンディング
・POC手段としてのクラウドファンディング
・クラウドファンディングと社会的インパクト投資
・資金調達ツールとしてクラウドファンディングの使い方
・起業家がクラウドファンディングで出来ること
その他
ご要望、お問い合わせは以下のフォームからお願い致します。
最新記事 by 西谷 佳之 (全て見る)
- 元銀行支店長が解説する貸金庫の仕組みと管理の実態 - 2024年12月28日
- 企業の女性活躍推進が進まない理由について ~施策や数値目標に焦点をあてることの限界~ - 2024年7月8日
- ピルの使用で女性と組織のパフォーマンスを上げる 「企業の福利厚生としてピルに注目するメリット」 - 2023年10月17日
