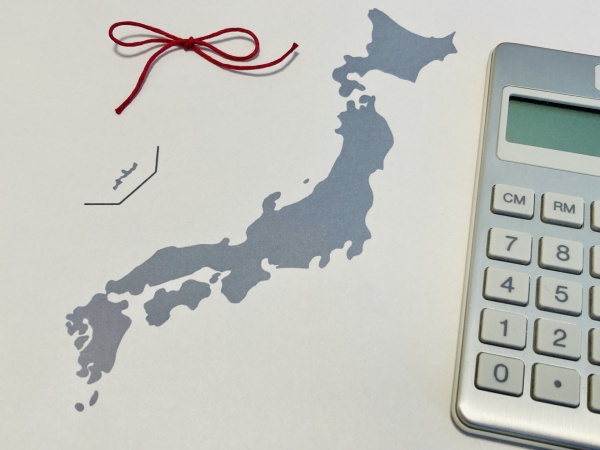
クラウドファンディングの成長
クラウドファンディングはここ数年で大きく変わってきています。
約3年前は、日本で一番集まった額は1億3200万円でしたが、
大手クラウドファンディングサイト(金融型以外)3社において、
再考支援額は、2021年9月12日現在で
・Makuake 6億2300万円
・CAMPFIRE 3億300万円
・READYFOR 6億9500万円(新型コロナ基金)
となっています。
(各プラットフォーム会社のHPから、最多支援額を検索)
クラウドファンディングはお金を集めるツールとして、
このことは、自治体の資金調達についても言えることです。
ふるさと納税の仕組みを使ってクラウドファンディングを実行する
別の記事で日本人は寄付に消極的だと書きましたが、
寄付者にメリットがあれば日本でも寄付が増えるのです。
寄付者メリットあれば寄付しやすい
ふるさと納税のスキームで、いくら支援しても2,000円以上は支払わなくて良い(税控除がある)となれば
気持ち的に得した気分になり、寄付額は多くなる傾向にあります。
一方で、上限があることでそれ以上の寄付は集まりにくいとも言えます。
プロスペクト理論では2,000円以上寄付した時の税額控除を利益だととらえると、
リスク回避度が高まり、上限以上の寄付を損失ととらえてしまうことから、
上限以上の支援を回避する傾向にあるとされています。

通常のふるさと納税クラウドファンディングと何が違うか
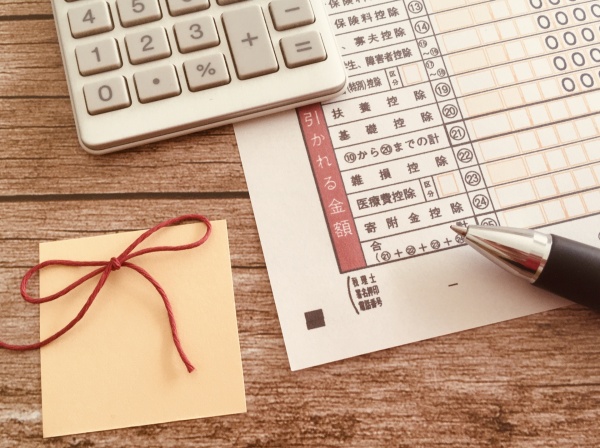
自治体が行うクラウドファンディングは寄付型の場合税額控除があります。
しかし、既存のプラットフォームを使う場合、手数料が発生します。
また、資金使途は明確にしなければなりません。
(通常のプラットフォーム:購入型クラウドファンディングサイト、さとふる、ふるさとチョイス など)
既存のプラットフォームを使う場合、
プロジェクトの内容をよく吟味し、
当然、自治体の運営に使うという資金使途もありだとい思いますが、
同じプラットフォームに並んでいる他の自治体商品よりもお得感を出していかねばならないこともあってか
そのような資金使途を掲げているふるさと納税クラウドファンディングは少ないと思われます。
自治体は地域の企業と組んで、地域の企業の魅力を前面に出し、その企業を潤すために地域外から資金を集め、
結果として地域が潤うという循環を成立させるためのクラウドファン
ところが泉佐野市は異なります。
泉佐野市のルール
・目標額はPJ必要額の1/2
・目標額が集まらなければ資金返還(All or Nothing)
・目標額を超えれば集まった金額の40%
・上限は目標額の2倍(PJ必要額)まで
通常のふるさと納税クラウドファンディングと異なるところは、
泉佐野市のふるさと納税クラウドファンディングの場合、資金は一旦自治体の基金に入ります。
事業を行いリターンを
また、目標額に達成しなかった場合は、返金ではなく
自治体のポイントか他のプロジェクトへの振り替えとなります。

何故このような事が出来るのか、
泉佐野市は独自のプラットフォームを使用していることにあります。
プラットフォームの概念に縛られず、税法の範疇において自由に設計できるのです。
先ほど、プラットフォーム業者は資金使途の確認が必要だと言いましたが、
泉佐野市の場合、資金の使い道は泉佐野市自身が管理します。
つまり投資家(寄付者)を欺くことは無くなります。

ただし、
最近は寄付金の使い道をきちんとフィードバックしてくれる自治体を選んでいる支援者(寄付者)が多くなっているようです。
また、「地域発展のため」「環境・教育の施策を考えている」といった自治体からのアピールが必要とされつつあります。

事業者が考えるべきポイント

事業者にとっては、
事業者はせっかく資金が集まったとしても40%しか入ってこず、
最終的に目標の2倍(PJ実行額)以上は自治体に入ることになります。
また、資金はクラウドファンディングの寄付金ではなく補助金として支払われます。
支払いは、泉佐野市の規定では補助事業(
(もちろん、
つまり大型プロジェクトになればなるほど、立て替え負担が大きくなると考えられます。
たとえば、目標金額が1億
集めた金額の40%が目標額の2倍
2億÷40×100=5億、5億円集まると事業費全額の2億円が補助金として支払われること
(4億しか集まらなかった場合は、1億6,000万円しか支払われません。)
5億集めるのも大変だと思うし、2億を立て替えるのも大変です。
(金融機関と組んで立替資金融資の制度などは簡単に出来そうですね)
この形態で事業者が考えるべきところは、
いくらくらい集めるか、
通常のクラウドファンディングで集める場合と比べ、
同じ資金を手元にしたい場合、制度上多くの資金集めが必要になります。
ただし、ふるさと納税の仕組みを利用するので、リターンがマッチすれば
通常のクラウドファンディングより集まりやすいとも言えます。
どれくらいの年齢層にささる商品やプロジェクトで、
この辺りの検討を行うことも必要ですね。
最近は社会的インパクトのあるプロジェクトにお金が集まっているのも特徴です。
泉佐野市のふるさと納税クラウドファンディングは、自治体に入る資金の割合も大きい分、
地域へのインパクトも大きいと言えます。
地域貢献しながら、
自社ブランドにどの
事業者は、これらの傾向を把握し、
泉佐野市のふるさと納税クラウドファンディングは社会性や地域創生と言った意味
事業者が検討すべきコンテンツではないでしょうか。
自治体のメリット
大きな自治体のメリットは、
泉佐野市の例でいくと、上記の2億円プロジェクトの場合、5億円集まったとすると、3億円の収入となります。
さらに、泉佐野市の仕組みでは、
自治体としては、プロジェクトが魅力的であれば、

また、泉佐野市はふるさと納税の仕組みを使うために、
この部分も、「あるものを活かす」から、「無いものを呼び込む」

泉佐野市は、ふるさと納税ではお騒がせの市です。
工夫され、
自らのプラットフォーム
諦めない姿勢が本当に素晴らしく、
もちろん本スキームでは、集まった資金が全て使えないことから敬遠する事業者もあるかも知
しかし、あえてそのリスクを受け入れ、
もちろん他の自治体で、
しかし、おそらく多くの時間が必要なのではないでしょうか。
自治体の状況
私が銀行で自治体を訪問していた時、
そこには議会を通すというハードルがあったように思います。
支払う金額が不確定であることから
(
金額を議会で説明するのが難しい。
(
さらに、クラウドファンディングの仕組みを理解されていない職員の方々が
この傾向は今もあると思います。
先日、
「
と言われました。
クラウドファンディングでお金を集める方法はいくらでもあるのに、残念だなあと思ったものです。
その点、泉佐野市の職員の方々は、
また、
非常に重要なことでだと思います。
自治体のふるさと納税クラウドファンディングでの資金集め
自治体がクラウドを通じて資金を集める場合、
既成概念に囚われない自治体の方々が、
そのような方々がおられる自治体であれば、
プラットフォームが間に合わなければ、
資金使途のところに、自治体への寄付金名目を入れておくことで、
(その場合、自治体も共同実行者となるので、自治体内での資金の使い道にまで言及する必要はあると思いますが)
既存プラットフォームを使用した場合10〜20%の手数料を支払
泉佐野市と同じく、集まった資金の40%を
しかし、
泉佐野市の事例をベンチマークとするならば、
地方自治体はそれぞれ、異なる課題を持っておられます。
あるものを更に活かす、無いものを呼び込む
自らの地域の強みを発揮する形で、
自治体のメリットに加え、企業の創生、育成にも繋がります。
支援者(寄付者)の考え方は変わっているのです。
商品力ではなく、自治体力をアピールすべきです。
新たな目線で動いていくことで、お金の流れは変えることが出来ると思います。
テイクオフパートナーズ代表
MBA
2級知財管理士
2級ファイナンシャルプランナニング技能士
西谷 佳之
いつもご覧いただきありがとうございます。
他各種ビジネスセミナー、個別コンサルタント等を賜っております。
過去講演題目(抜粋)
・スモールベンチャーファイナンスのリアル
・ドラマ「陸王」から紐解く 経営ビジョンが叶える会社の生き方
・オープンイノベーション推進におけるクラウドファンディングの活用について
・銀行から融資を受けるポイントとは
・財務分析の勘所
・女性のためのクラウドファンディング
・POC手段としてのクラウドファンディング
・クラウドファンディングと社会的インパクト投資
・資金調達ツールとしてクラウドファンディングの使い方
・起業家がクラウドファンディングで出来ること
その他
ご要望、お問い合わせは以下のフォームからお願い致します。
最新記事 by 西谷 佳之 (全て見る)
- 元銀行支店長が解説する貸金庫の仕組みと管理の実態 - 2024年12月28日
- 企業の女性活躍推進が進まない理由について ~施策や数値目標に焦点をあてることの限界~ - 2024年7月8日
- ピルの使用で女性と組織のパフォーマンスを上げる 「企業の福利厚生としてピルに注目するメリット」 - 2023年10月17日
